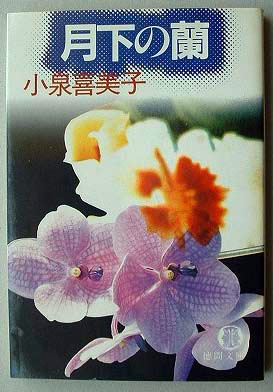FILE07 菊地秀行&小泉喜美子
美貌の都――菊地秀行さんについての覚書(祥伝社ノン・ポシェット『夜叉姫伝(1)吸血麗華団の章』解説)
「121世紀だったかな、核戦争で人類の文明が破滅して百世紀経過したという遙かな未来のお話なんだけど、18くらいの飛び切りの美青年が主人公でね、これがダンピールといって、吸血鬼と人間の混血(あいのこ)で、しかも吸血鬼ハンターなの、筋も中々よく出来てるし文体も悪くないんだ……」というようなことを私の耳に囁いたのが誰であったか想い出せないが、この情報には私のウィークポイントを突くところがあって、何だかシチュエーションが少女漫画っぽいなと思いつつも、私は早速に『吸血鬼ハンター"D"』を購読したのであった。
今、手許の文庫本の奥付を見ると、「昭和58年3月20日 2刷発行」とあるから、だいぶ前の事になるが、ともかく面白くて一気に読み通したという記憶が鮮明に残っている。まず驚いたのは漢語(蒼穹・跳梁・跋扈・刹那……)や文語的措辞(すべからく・寂寞たる・白蝋のごとき……)が頻出することで、あまり改行しない事と併せて、私には歓迎すべき殊色ではあっても、エンターテインメントの読者一般にはそっぽを向かれるのではないかと余計な心配をしたほどである。
文体は端正であり、ダンピールという主人公のキャラクターも画期的なものであった。吸血鬼と人間との間に生まれた者という設定(吸血行為がセックスを兼ねるという吸血鬼の生理からすれば、かかる事態については、いずれ然るべき説明がなされねばならぬだろうが……)は欧米の作品にもあまり類が無いと思われ、まさしく会心のアイディアと申すべきであろう(映像作品には『キャプテン・クロノス』という吸血鬼ハンターものがあった)。そして何よりも感慨深かったのは、漸く日本人の手に成る本格的な長篇吸血鬼小説の登場を目(ま)の当たりにしたという事であった。
第二作の『風立ちて"D"』はセンチメンタルでノスタルジックな標題からして何とも好もしく、またプロットも第一作に劣らぬ好篇であった。かくして私は【Dシリーズ】の刊行を待ち焦がれる愛読者となったのだが、その最大の要因は〈吸血鬼テーマ〉と〈主人公の美貌〉にあり、即ちこれが私のウィークポイントであった。
こんな事を書き始めた私は、そも何者なのか……大方の読者は御存じないと思われるので、厭味と取られぬよう心がけながら自己紹介を挟んでおきましょう。私が吸血鬼に興味を抱いたのは1960年代、十代の半ばを過ぎた頃の事で、むろん外国の吸血鬼映画(多分『吸血鬼ドラキュラの花嫁』か『血塗られた墓標』)に感化されたのだと思う。本が好きだったので吸血鬼の小説を探したが、当時はストーカーの『ドラキュラ』の抄訳本くらいしか出ていなかった。『ドラキュラ』の完訳が出たのは1971年で、その頃から漸く英米の短篇を集めたアンソロジーなども出始めたものの、日本の作家の筆に成るものは殆ど無かった。『ドラキュラ』はもとよりレ・ファニュの『カーミラ』もゴーティエの『死女の恋』も傑作だと思ったが、ポリドリの『吸血鬼』を除けば悉く〈吸血鬼退治譚〉であり、そこに些少の不満を覚えた。私は、吸血鬼を〈恐怖を煽る妖怪〉とは捉えず、ひたすら憧憬の対象として仰ぎ、吸血鬼小説にエロティシズムを求めていたのである。裏地の鮮やかに紅い黒マントを優雅に翻しつつ夜の世界を称揚する陰鬱なる美青年――というのが私の思い描く理想の吸血鬼像であった。
60年代の終り頃から物を書き始めていた私は、勧めてくれる人もあったので、その頃見たヴァディムの『血と薔薇』やポランスキーの『吸血鬼』などに想を得て、我が想う吸血鬼が登場する掌篇を発表し始め、74年に吸血鬼譚をまとめ『就眠儀式』と題して刊行した。それまで吸血鬼譚集などというものは出た事がなかったし、また旧仮名正字を用いているから、多分売れないだろうと思っていたが、何年かの間に再版が出て新装版も出た(とはいえ部数は僅かである)。その後、78年に『血のアラベスク――吸血鬼読本』という概説書のような本も出し、頼まれればエッセイや短篇も書いた。
吸血鬼に関する著作は私の仕事のごく一端にすぎないが、吸血鬼に対する関心は今に至るまで持続しており、その途次で菊地さんの【D】シリーズに出遭えたのである。このシリーズの七作目に当る『D――北海魔行』が出て暫く経った頃、菊地さんが新たに長篇吸血鬼小説を執筆連載しているという情報が齎された。『夜叉姫伝』と題するその長篇の第一巻が新書版で出るのを待って購読した頃、思いがけず菊地さんに見(まみ)える機会を得た。雑誌「幻想文学」が吸血鬼の特集号を出すことになり、私に菊地さんと対談する役目が回ってきたのである。本の後記やエッセイ類の書きぶりから推して、わりと威勢のいい人なのかなと安易に想像していたのだが、お目にかかってみると、謙虚というか遠慮深いと申すべきか、実に奥ゆかしい方だったので、ちょっと面くらったが、あの端正で時に古風な趣さえ湛える文体に照らせば、むしろ当然の事かとも思い至った(後に、武道に関する求道的な雰囲気の御本を頂戴した折には、また別の一面を垣間見る思いがした)。
お喋りな私がべらべらと自説を捲し立てるのを、菊地さんは穏やかな表情で我慢強く聞いて下さったが、映画の話題になると流石に膨大なコレクションの持主ゆえ、疎(うろ)覚えの私などの敵するところではなく、聴くべき所が多かった。ルーマニア旅行のお話も私には貴重に思われた。私のほうが幾つか年嵩だが、さほど懸け離れてもいないせいか、隔靴掻痒という感じはなくて、かつての新東宝のエログロ映画の話題などで盛り上がった。これが御縁となって、もう一度見たいと願っていた映画(もちろん吸血鬼物が主だが、サイレント時代のドイツ映画など貴重なフィルムも)のビデオを度々拝借するという幸運に浴している。
菊地さんは学生時代に私の『就眠儀式』を読んで下さった由にて、「羨ましかった」と仰って下さった。もしあのようなささやかな掌篇集が後の菊地さんの長篇吸血鬼譚執筆に聊(いささ)かなりとも寄与する所があったのだとすれば嬉しいかぎりだが、むしろ羨望の念を禁じ得ないのは私のほうで、どう足掻いても百枚くらいのものしか書けぬ私には、菊地さんの卓越した長篇構想力が驚異的と映るのである。
エンターテインメントの長篇と申すものは、シチュエーションが見事であればあるほど、局を結ぶのが難事であり、終局に至って腰砕けを曝す傑作もどきの例は枚挙に暇(いとま)もないほど見出されるし、波瀾万丈息をも吐(つ)かせぬ体の『大菩薩峠』『乱菊物語』『神州纐纈城』などはみな未完に終っている。菊地秀行の長篇は、このあたりに工夫が凝らされているように見受けられる。たとえば【D】シリーズは、連作という形式を採り、貴種流離譚とも年代記とも読めるように書かれている。魅惑的なキャラクターを一つ作れば半永久的に書き継げるわけである。これを更に壮大になしたのが【魔界都市】シリーズであり、『夜叉姫伝』はその成功の上に構築された新たな物語ということになる。
魔界都市〈新宿〉にも吸血鬼は既に存在していたが、ここに想像を絶する古代から暗黒の世界をさすらい続ける強力無比の吸血鬼たちが侵略者として現れる。五号街路が時ならぬ水に涵されて川と化し、一艘の木造船が闇の奥から幽霊船さながらに現れるのを、美貌の煎餅屋・秋せつらは見る。美貌の、或いは異形の四人が姿を現すが、琴の音が響き、「渡水復渡水、看花還看花、春風江上路、不覚到君家」と異国の詩が吟ぜられ、吸血鬼たちの出自は中国と知れる。因みに件の詩篇は、明(ミン)末・清(シン)初の乱世を生きて39歳にて刑死した天才詩人・高青邱(コウセイキュウ)の「尋胡隠君」である。
中国とはまた!――と私は、この作者の尽きざるアイディアに感嘆した。二十数年前に香港で『七屍金』なる吸血鬼映画が作られているが、これはドラキュラが中国に出張して来るだけのものにすぎない。あと思い中(あた)るのは山尾悠子さんの短篇「支那の吸血鬼」と日影丈吉の台湾ものの短篇くらいで、未だかつて中国人の吸血鬼が跳梁する本格的な長篇など誰も書いていないのである。四千年の〈死を生きる〉美貌の吸血姫には『三国妖婦伝』で名高い妲妃(ダッキ)その他の悪魔的美女の面影が附与されている……などと一々挙げても詮ないこと、伝説・神話時代の中国の美味しい所を撰んで巧緻に織り込んだ〈いいとこ取り〉なのである。
そして、「身の毛もよだつ美男医師」と「美しき魔人」、即ち「魔界都市の美と戦慄を象徴する男たち」に加えて、或いは彼らの美を凌ぐという「姫」、更に夜香・秀蘭・劉貴・高子らの美男美女を配する本篇は〈菊地美貌小説〉の究極と言ってもいい。彼らは唯の美形ではなく、「僕」と「私」を使い分ける煎餅屋を筆頭に例外なく翳りを帯びた重層的キャラクターに設えられていて、然も男女を問わず虜にするアンドロギュヌスでもあり、ここらが並のエンターテインメントと断然異なるところである。
菊地さんと私に共通点があるとすれば、吸血鬼小説は陰鬱な美青年の物語であり、襲う者も襲われる者も美貌に設定しなければ気が済まないという思いかも知れない。ただ、持久力と構想能力に欠けるため短篇で切り上げてしまう私などと違って、大長篇の筆力に恵まれている菊地さんは脇役のキャラクター造りにも秀でていて、この作でも騏鬼翁とか、後半に活躍する女魔道士ガレーン・ヌーレンブルクなどは見事に造形されている。殊にガレーンの人形娘は、菊地さんには何やら特殊な御趣味があるのではないかと疑いたくなるくらい素敵で、私の一番のお気に入りである。
申し遅れたが、『夜叉姫伝』はアン・ライスの【レスタト】シリーズやR・R・マーティンの『フィーヴァー・ドリーム』と列ぶ現代長篇吸血鬼小説の傑作である。
(平成9年6月)

月影に咲く蘭の花――小泉喜美子の情熱
(徳間文庫『月下の蘭』解説)
ユイスマンス『さかしま』より新しい香料や見たこともないほど大きな花々や、
味わったこともない快楽を、
あたしは探しに 行くんだよ……
小泉喜美子さんには『メイン・ディッシュはミステリー』と題する海外ミステリーの案内書とも申すべき著作がある。永きに亙って海彼のミステリーを愛読し、また多くの翻訳を手がけている小泉さんにしてはじめて書き得た好著であり、「ミステリーには本道も邪道もない。あるのは、いい作品と悪い作品だけである」という見識のもとに選ばれた〈現代の海彼のミステリー〉の一級品が紹介されている。海彼のミステリーを読むための指針として、まず申し分のないものであるが、更に好もしいのは、小泉さんのミステリーに対する真摯な姿勢(実作者としての、また読者としての)が随所に見られることである。
事は、ミステリーという小説分野の定義にかかわるのだが、日本のミステリー愛好家の間に根強く蔓延(はびこ)っている〈本格物信仰〉という一種の怪物を相手に、小泉さんは《真のミステリー》とは如何なるものかという事を執拗に辛抱強く説いており、その熱意と愛情には、同憂の一人として敬服せざるを得ない。就中(なかんづく)次のごとき一節には、実作者としての小泉さんの毅然たる態度が能(よ)く示されている。
ひとたび、「ミステリー」と銘打って読者の前に送り出されるからには、それは豊かで楽しく美しい、技巧と感覚とを重んじる魅力的な小説分野でなくてはならぬ筈である。悲惨・陰惨な殺人や凶悪犯罪、人間社会のいちばん醜悪な面を題材として好んで扱うゆえになおいっそう、それは美しくなくてはならない(「なおいっそう」以下傍点)。形式において、表現において、洗練度において、ミステリー作家は自己の全力を傾けてそれ(2字傍点)を幼稚な推理クイズやナマの犯罪ばなしとは劃然(かくぜん)とへだてて見せなくてはならない。それでなければ、ミステリー作家の道をわざわざ選ぶ意味がないのである。(と私は信じている)斯(か)く言挙げするからには、中途半端な作品など発表できよう筈がない。はたして、小泉さんの小説は、常に技巧と感覚を駆使した魅力的なミステリーに仕上げられている。殊に長篇の出来映えは類少なきものにて、処女長篇『弁護側の証人』以来、一作ごとに巧緻な仕掛が施され、心にくい趣向が凝らされてきた。その一端を挙げれば、『弁護側の証人』ではシンデレラ伝説が、『ダイナマイト円舞曲(ワルツ)』では青鬚伝説が、『血の季節』では吸血鬼伝説が、即ちヨーロッパの三大伝説がそれぞれ仕掛や趣向として採用され、実に巧みに消化=昇華されている。
こう記すと、小泉さんの小説は技巧一点張りのものと誤解されかねないが、さにあらず、どの作品にも〈心意気〉とか〈心延(こころばえ)〉とでも申したらいいような一種気概のごときが漲っており、それは例えば泉鏡花の小説や久生十蘭の戦後の短篇に認められる〈潔さ〉を想い出させるところもあり、またレイモンド・チャンドラーなどの上質のハードボイルド物に通じているとも思われる。そしていま一つ、小泉さんの持論を裏付けるように、手法・作風とも、歌舞伎(当然先行する浄瑠璃戯曲を含む)の作劇法に通ずるものがあると申せよう。
ミステリーの愛好家も歌舞伎の愛好家も世には多く在ろう、ミステリーと歌舞伎の両方を愛する人も多少は在るに違いない。歌舞伎を扱ったミステリーも皆無というわけではなく、小栗虫太郎の「人魚謎お岩殺し」、戸板康二の「車引(くるまびき)殺人事件」以下の中村雅楽シリーズ、赤江瀑の「獣林寺妖変」などが想起されるが、いずれも事件の背景を歌舞伎の舞台裏に設定したもので、約(つづ)まるところ題材としての扱いにとどまっている。
「日本の歌舞伎や浄瑠璃にはそれこそ何百年も昔に書かれた楽しいミステリーの原型がある」と述べて、歌舞伎とミステリーの共通点を明確に指摘したのは、おそらく小泉さんが嚆矢であろうし、単なる題材としではなく意識的に歌舞伎の手法を採り入れてミステリーに活かしたという人も小泉さんのほかには思い中(あた)らない。『月下の蘭』初刊本の「あとがき」には、〈ミステリーと歌舞伎の共通点〉として、次の四箇条が掲げられている。
右のうち、小泉さんにとって特に重要かつ切実だと思われるのは、第二・第三の項目であろう。浄瑠璃や歌舞伎の狂言=演目には〈世界〉というものがあり、その演目の時代背景や登場人物を特定する。〈世界〉はよく知られた古い物語や伝説に求められ、〈御位争(みくらいあらそい)の世界〉とか〈出世奴の世界〉とかが常に狂言を支配するのである。例えば、『假名手本忠臣藏』は〈太平記の世界〉であり、『助六』は〈曾我物語の世界〉であるが、衣裳などの風俗は殆ど現代(徳川時代)のそれである。これは、もとはと言えば、〈現代の武家社会〉をそのまま劇化する事が禁じられたために採られた方便であったが、却って現実から遊離することによって奔放かつ壮大なるスケールを獲得したかのごとくである。全てを遠い昔の夢まぼろしのように作り成しておきながら、言うべき事は抜かりなく書き込んでいる。小泉さんが「遊びに託して真実を語ろうとしてきた」と記す所以であろう。○どちらも永い伝統を具えた娯楽である。それなりの成立過程を持ち、しかも常に新しく脱皮しようと努力してきた。
○単に先行作に追従するのではなく、前作をいかにもじり(3字傍点)、パロディ化するかという点に生命を賭けてきた。
○ナマの現実をそのまま表現するのではなく、遊びに託して真実を語ろうとしてきた。(明治以後のいわゆる「活歴」や史劇のたぐいは私は歌舞伎とは考えていないし、日本社会派なるミステリーもミステリーとは認めていないことと同じくである)
○どちらも様式のととのいを重んじている。これなくしてはどちらもあり得ない。
また「前作をいかにもじり、パロディ化するかという……」云々に関しては、『東海道四谷怪談』が『假名手本忠臣藏』の、『助六』が曾我狂言(新年に江戸三座にて上演)対面の場の、『切られお富』が『切られ与三』の、それぞれパロディである……と申せば了解されるだろう。そして、小泉さんの長篇は全てこれを実践したものである。『弁護側の証人』は世界を「シンデレラ」に求めると同時にクリスティーの『検察側の証人』のパロディであり、『ダイナマイト円舞曲』は世界を「青鬚」に採るとともに歌舞伎の『先代萩』のパロディであり、『血の季節は』は極めて意図的に「吸血鬼の世界」を扱っている。しかも前(さき)に述べた通り三作ともに〈心意気〉とでも申すべき気概が看取され、これは「遊びに託して真実を語る」姿勢に通じるかと思う。
連作短篇集『月下の蘭』即ち本書では、更に歩を進めて、歌舞伎の所作事(舞踊劇)や能の名作を直接モティーフにするという、かつて誰も手がけた事の無い試みに挑戦している。申さば、歌舞伎狂言における〈書替〉という手法の実践である。主題は悉く復讐、ともかくも典拠を挙げておこう。
「月下の蘭」――「雙面水照月(ふたおもてみづにてるつき)」
「残酷なオルフェ」――「田舎源氏露東雲(つゆのしののめ)」
「宵闇の彼方より」――「土蛛(つちぐも)」
「ロドルフ大公の恋人」――「積戀雪關扉(つもるこひゆきのせきのと)」
登場人物の名前などは相応に原作を踏襲しているもの、筋をそのままなぞっているわけではなく、いずれも原典の香りを現代に移して新たなる物語に織り直した佳作である。
「月下の蘭」は〈人面花〉を扱ったファンタジーと申せようが、題材としてはたいへん珍しいもので、類似作としては僅かに大坪砂男一代の傑作「零人」、また山田風太郎の怪作「人間華」などが想い起される程度である。終章の温室内の描写を読むとき、私はいつも「Orchids in the moonlight」という古いタンゴ(ハリウッド映画『空中レビュー時代』挿入歌)が聞えてくるような思いを味わう。
新劇俳優の恋の葛藤を描いた「残酷なオルフェ」は集中最も現実味の濃いミステリー。これのみ一人称で書かれている。「宵闇の彼方より」は外枠つき二重構造の幻想味濃きミステリーと申すべきか。銀世界に極彩色の大極楽鳥が羽ばたく――という幻影がくっきりと眼に灼きついて残る「ロドルフ大公の恋人」に私は最も惹かれる。精霊物の原典が見事に書替えられているが、鳥の雄が人間の女に変幻して現れるかのごとき錯覚を覚えさせるところが凄い。
最後に、小泉さんが歌舞伎について思う存分語っている『やさしく殺して――ミステリから歌舞伎へ』の中から蠱惑に満ちた一節を引用したい。
この條(くだり)を読むたびに、かつて舞台の上に見た美しい男や女――緋の八重垣姫と紫の勝頼と黒の濡衣(ぬれぎぬ)が、灰色の仁木彈正が、振袖の下に刺青(ほりもの)を隠した辨天小僧が、嫣然と笑む花魁(おいらん)八橋が、櫻姫に狂う破戒僧清玄が……眼交(まなかい)に押絵のごとく迫(せ)り出してきて、私は胸苦しさを覚える。小泉さんの情熱が文章に乗り移って読む者を唆(そそのか)すのであろう。……私はいつでも詩や童話や幻想のいっぱい詰まった美しい絵本をめくるような気持で歌舞伎を見ているのだ。恐怖や戦慄や奇怪な快楽のいっぱい詰まった、動く絵本を。
ときに、その絵本の図柄は、香煙のむせかえる冬の館である。恋し合う緋と紫と黒の男女がゆるやかに交錯する。白刃をかざした刺客は美青年のあとを追って行く。彼らが横切る荒野の果ての氷のような月を、月のような湖を、私たちは想像することができる。それはドラクロワの絵のように美しく、おそろしい光景である。また、ときに、その絵本の図柄は、地の底から忽然と出現する灰色の妖術師である。両性具有(ふたなり)の美貌の不良少年である。田舎者を嘲笑うダリアのような高級娼婦(クルティザン)である。破滅へ向ってまっしぐらに堕ちて行く若き僧である――
(1985年7月)